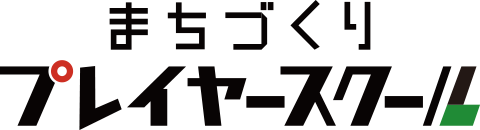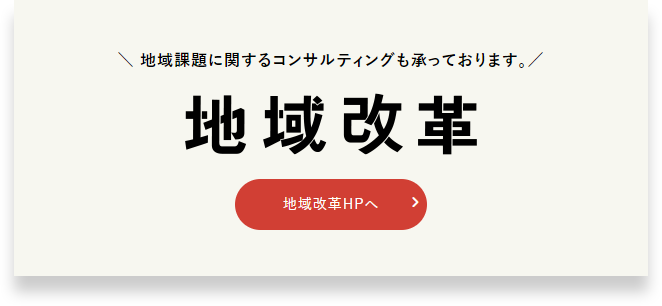企画が成功するための核心は、「動機」にあります。
企画名を見ていて「これはどんな動機があるのだろうか?」と疑問に感じることがよくあります。実際、社員や伴走支援の経験から、はじめから明確に動機を定義して企画を立てることができているケースは非常に少ないのが現状です。そのため伴走支援では「参加の動機は何ですか?」「どのような動機でしたか?」という質問をよく投げかけます。
具体例として、高架下のスペースを使った企画を見てみましょう。
A:さまざまなイベントを行う「高架下フェス」
B:ストリートカルチャーを楽しめる「ストリートカルチャー体験イベント」
どちらが参加したい動機を引き出せるでしょうか。Aは漠然としていて動機が薄く感じられますが、Bであれば「ストリートカルチャーを体験したい」という明確な動機が生まれます。Aでも成功する可能性はありますが、動機を意識した企画は圧倒的に成功の確率が高まります。
私は21歳から数多くの企画を実施してきましたが、集客において高い成果を出すことができました。その経験を振り返り、成功と失敗を分析した結果、「最初の動機設計=コンセプト設定」が成功の鍵だと確信しました。企画は初期段階の設定で成否が大きく分かれ、初動を間違うと後から修正するのは困難になります。成功するための正しい道筋を作り、その道筋をきちんと進めば必ず成功します。企画成功は決して運ではなく、明確なロジックに基づいているのです。
弊社では人材育成事業において以下のポイントを中心に伝えています。
① 明確な動機を生むコンセプト作り
② 動機を具体的に反映するコンテンツ作成
③ 正しいコンテンツ作成手順と成功のポイント
【動機が強いほど成功しやすい理由】
「マーケティングファネル」という言葉をご存知でしょうか。消費者が認知してから実際に行動する割合はほんの数%と言われています。これは企画にも同じことが言えますが、この割合は動機を強化することで大きく引き上げることができます。「興味がある」から「絶対に参加したい」に動機を強化することで、行動への転換率を高めるのです。
例えば、次の例を見てください。
① ビアガーデン
② オクトバーフェスト
③ 世界のビール100種を楽しむワールドビアフェスタ
①から③にかけて動機は明らかに高まります。こうして動機レベルを引き上げることが企画成功への近道です。
【ただ動機が強ければいいわけではない】
しかし、動機を強くすることには次のようなデメリットもあります。
・必要なリソース(時間や費用)が増える
・ターゲットが狭まり参加者層が限定される
特にリソースの増大は収益面で深刻な問題となり得ます。例えば上記の③のビールイベントは、準備や運営にかかる費用が非常に大きくなり、利益を出すのが難しくなる可能性があります。
【動機設定は参加ハードルを考えることから】
行動には距離、費用、申し込みの手間、アクセスの良し悪し、過去の参加経験など、さまざまなハードルが存在します。企画は手をかければ際限なく改善できますが、収益性を考えるなら、まず企画成功の基準を設定し、参加を阻害するハードルを超えるだけの動機レベルを設定したコンテンツを作る必要があります。これを弊社では「動機レベル設定」と呼んでいます。
このノウハウは120分間の講座で提供していますが、知識だけでは実践的に定着させることは難しく、実際の伴走支援で繰り返し動機を確認しながら指導していくことが必要です。弊社の社員も初めは難しかったものの、現在では動機の重要性を深く理解し、頻繁に動機という言葉を使っています。「なぜこんな大切でシンプルなことに気付けなかったのか」と感じるほど、その重要性を実感しています。
この記事はノウハウの一部を簡潔に紹介しております。
手法・事例の詳細は文字では全て書ききれない為、省かせて頂いております。
伴走支援では、プレイヤーの事業を通してノウハウを活用し支援・育成を行っております。