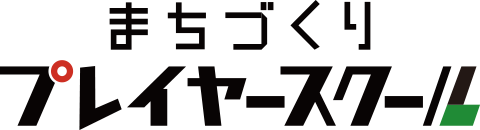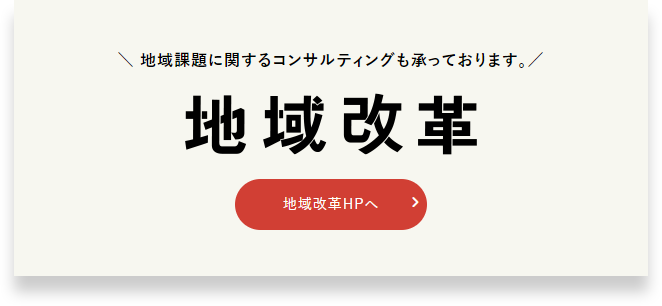商店街活性化とは?
商店街は、もともと「商業集積地」として発展してきた場所です。
その本質を考えると、商店街の一番の活性化は「商業活性化」であると考えています。
つまり、シンプルに言えば「商売して稼げる地域かどうか」が重要です。
よく耳にする「賑わいの創出」や「コミュニティ形成」といったキーワードは、どちらかといえば“目的”ではなく“手段”に近いと捉えています。
実際には、商業活性化を進めていく過程やその延長線上で、自然と賑わいやコミュニティが生まれてくるケースが多く見られます。
人は動機から行動する
人は動機があってこそ行動します。
商店街に足を運ぶのも同じで、「欲しいものがある」「楽しいことがある」「見てみたいものがある」といった動機によって行動が生まれます。
そして、こうした動機の多くは、ハード(設備や施設)からではなく、圧倒的にソフト(企画やコンテンツ、体験など)から生まれることが多いです。
もちろん、商店街におけるハード面への投資も必要です。しかし、商店街にとって最も重要な目的である「商業活性化」に必要なのは、やはりソフトの力です。 多くの動機がソフトによって生まれ、人を惹きつけ、結果として売上や集客につながっていきます。
余談ではありますが、商業活性化という観点で見た場合、再開発などの大規模なハード投資が行われると、テナントの家賃が上がり、結果として粗利が圧迫されることがあります。
そのため、ハード投資が必ずしも商業活性化に効果的であるとは言い切れません。
商店街のソフト事業は主に「共同販促」
商店街におけるソフト事業の中心は、「共同販促」であると考えています。
個店単位(点)ではなく、商店街全体(面)として一体的に取り組めるのは、商店街ならではの大きな利点です。
共同販促は、各店舗が単独で行う販促活動に比べて、コストパフォーマンスが高まりやすいという特徴があります。
具体的には、「イベント」「キャンペーン」「情報発信」「勉強会」などの形で展開され、商業活性化と消費者の満足度の向上を同時に実現することができます。
実際、商業施設などでは、さまざまな共同販促を通じて“稼げる・魅力あるエリア”を形成しており、それが継続的な商業活性化を生む要因となっています。
私自身、全国各地の現場で商店街再生に関わる中で、共同販促こそが商店街再生のエンジンであると確信しています。
「効果的な共同販促を、どれだけ効率よく、多く実施できているか?」
この問いに対する実践度が、商店街の商業活性化の成否を大きく左右します。
実際に、効果的な共同販促が数多く行われている商店街は、その多くが商業が活性化しています。
また、疲弊した商店街ほど、エリアコンセプトを策定し、ブランディングを進めていくことが効果的です。これらの取り組みも、共同販促の一環であり、事務局が担うべき重要な役割となります。
商店街組織の課題
効果的な共同販促を実施したいと考えている商店街は多いものの、実際にはほとんど行われていないのが現状です。
弊社が行った調査によると、年に4回程度の共同販促が実施できていれば非常に良い方であり、実際には年1回程度にとどまっている商店街が大半を占めています。
では、なぜ共同販促の実施が進まないのでしょうか?
その要因の一つは、商店街組織の“仕組み”にあります。
多くの商店街では、固定会費を徴収しており、その使途は主に「ハード(街路灯の電気代や清掃費など)」と「ソフト(販促費など)」に分かれています。
ハード面の費用は、一定の維持管理費として固定で捉えて問題ありませんが、ソフト面の費用については、現状の仕組みではうまく機能していない場合が多く見られます。
というのも、商店街には飲食店、アパレル、美容室、エステ、マージャン店、コワーキングスペースなど、多様な業態が混在しており、全店舗にとって“等しくメリットのある販促”を設計しようとすると、どうしても抽象的な内容になりがちです。
その結果、「スタンプラリー」や「駐車場無料券」など、効果の薄い企画になってしまい、消費者の満足度も得られにくくなります。
さらに、合意形成に時間を要するため、スピード感を持った展開が難しくなり、その調整や準備にかかる人件費がかさむなど、非効率な運営が続いてしまいます。
このように、固定会費による販促活動が、かえって商店街運営の足かせとなっているのです。
その結果、商店街に所属するメリットを感じられない店舗が離脱し、会員数が減少していきます。
そして、会員数の減少によって、残った店舗の会費負担(特にハード面)が相対的に増加し、さらに退会者が増えるという悪循環に陥ってしまいます。
会員ではないけど、ハードの恩恵をうけているという矛盾も生じています。
商店街活性化の鍵は「生産性のある事務局」形成にある
現在、多くの商店街では、商店主が理事として活動の中心を担っています。
しかし、事業の傍ら“片手間”で行っていることが多く、その活動にはどうしても限界があります。
たとえば起業においても、副業として行うのと、本業として専念するのとでは、成功の確率が大きく異なるのは言うまでもありません。
商店街事務局の運営もまったく同じです。限られた時間と人材という“中途半端なリソース”では、商店街の活性化は期待できません。
まず必要なのは、「時間」を確保し、「ノウハウ」を取り入れることです。
これにより、いわゆる“優秀な事務局”、すなわち「生産性のある事務局」を形成することが可能になります。
無形であるソフト事業は、ハード事業以上にノウハウの影響を大きく受けます。実施する人によって、その成果は1にも10,000にもなり得ます。それだけに、ノウハウの力がより強く問われる分野であると言えます。
では、「生産性のある事務局」とは何か。
それは、効果的な共同販促を次々と実施し、商店主の企画参加費だけでなく、商店街外からの広告協賛なども獲得し、自らの給料を自らの力で創出する事務局を指します。
弊社では1つの企画に対して1社から25万円~150万円の広告協賛を得ます。
これにより、自分達の給料を生み出しています。
弊社では、このような仕組みのもと、事務局が固定会費を徴収することなく、自ら販促企画を立案し、各商店に提案を行います。
商店主は、企画内容と費用を確認したうえで、「これは参加したい」と思うものにのみ参加するため、強制力がなく、デメリットもありません。
この仕組みの大きな特徴は、“合意形成を必要としない”点にあります。
そのため、スピード感を持って、尖ったテーマの企画を複数実施することが可能になります。
実際に弊社でもこのスキームを活用し、様々な共同販促を展開していますが、逆に固定会費がある方が運営しにくいと感じることもあります。
「生産性のある事務局」が確立されれば、商店街には自然と商業活性化がもたらされます。
本気で稼げる商店街を目指すには、まずこの“仕組み”を整えることが第一歩なのです。
どのように生産性のある事務局を形成するのか
生産性のある事務局を形成するためには、適切なノウハウがあれば実現可能です。その主な要素としては、「企画構築」「広報」「収益化」「プロジェクトマネジメント」など、多岐にわたります。
では、それらを誰が担うのか。多くの場合、商店主である理事の方々が対応されているケースが見受けられますが、本業をお持ちの中で活用できるリソースには限りがあります。商店街全体のために尽力されている理事の皆様は、本当に素晴らしい存在だと感じております。しかしながら、リソースには明確な限界があるのも事実です。
そこで、弊社では以下の3つの形を提案・コンサルティングしております。
① 社員雇用による対応
② 委託人材契約による運営 ※商店街の代理店的な立ち位置
③ 商店街理事による対応 ※感情対価の範囲で行うことが前提
弊社が最も推奨しているのは、②の「委託人材契約による運営」です。商店街にとってはリスクがなく、事務局側も良い企画を増やさないと稼げない為、生産性の向上にもつながります。
それぞれの状況に応じて、最適な形を選択することが重要です。
弊社では、全国各地でまちづくりのコンサルティングを行っておりますが、共通して重視しているのは、「地域の人材と共に事業を推進し、弊社の関与が終了した後も地域が自立して継続できる仕組みを構築すること」です。
この取り組みこそが、まさに「生産性のある事務局形成」の具体的なスキームとなっています。
まずは、人材を配置して“時間”というリソースを確保します。
その上で、様々なノウハウを提供し、広報・収益化・運営体制の整備を通じて事業構築を支援します。
最終的には、地域の事務局が自らの力で回る「自走型の組織」へと成長することを目指します。
全国の商店街が疲弊するなかで、解決の方法は一つではないと考えています。
しかし、弊社がこれまでの現場経験から最も効果的だと感じているのが、この「生産性のある事務局形成」というソリューションです。
この記事はノウハウの一部を簡潔に紹介しております。
手法・事例の詳細は文字では全て書ききれない為、省かせて頂いております。
伴走支援では、プレイヤーの事業を通してノウハウを活用し支援・育成を行っております。