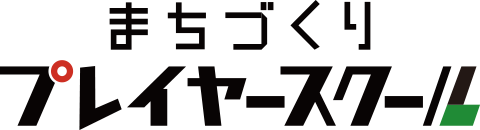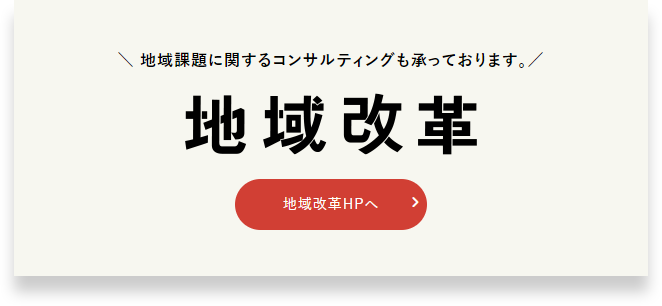まちづくり活動を続ける「収益構造」の壁にぶつかる
まちづくり活動を続ける中で、多くの方が直面する最大の課題は「収益構造」です。実際、まちづくりが続かない主な原因は「対価の欠如」にあります。
感情対価から金銭対価を得るフェーズに移行しても手法が分からないケースが殆どです。
参照:まちづくり活動が続かない本当の理由は「対価の欠如」 – まちづくりプレイヤースクール
弊社では、伴走支援を行う中で最も頻繁に受ける相談がこの収益構造の問題ですが、独自のノウハウを活用することで解決をしております。
まず、収益化のためには、以下の2つのポイントが重要です。
① 収益金を増やすこと
② 人件費を効率化すること
多くの方が収益金を増やすことだけに意識を集中させがちですが、実際には人件費の効率化も同じくらい重要です。自分の人件費を意識せず定量化しないことで、収益化に向けた戦略がつくれていない方は非常に多いです。
これだけの人件費(給料)を得たいから、この企画を〇日で実施する。それが可能かの戦略を立てているか?多くが立てていないと思います。
例えば、100万円の収益を得るのに、4ヶ月かかる場合と1ヶ月で済む場合とでは利益率は4倍も異なります。 ちなみに、弊社の社員は、入社後1年でその効率性を平均3倍に向上させています。
収益金を得る方法は?
収益金を得る方法としては、主に以下のようなものがあります。
❶ 協賛金
❷ 入場料・参加費
❸ 補助金(別記事で説明予定)
❹ 委託金
❺ 行政委託金(別記事で説明予定)
今回は、その中でも特に収益性が高く、継続しやすい「協賛金」についてご紹介します。
多くのまちづくり活動での協賛金は、地域貢献を目的とした「意義協賛」や、人間関係に基づく「お付き合い協賛」に偏りがちです。しかし、これらには限界があります。
私自身も若い頃、ボランティアでイベントを開催し1企画で300万円ほどの協賛を集めたことがありますが、その理由の多くはお付き合いであり、イベントの回数が増えるにつれて協賛が難しくなり、継続性を欠きました。 また、自分の人脈を削っている感覚もありました。 そこで生み出したのが「まちづくり活動の広告化」という手法です。
広告とは何か
広告は、新聞やテレビ、ラジオ、フリーペーパー、WEB、SNS、イベントなど、多様なメディアを通じて行われる広報活動を指します。2021年の日本の広告費は約6兆8千億円で、2023年には7兆3千億円に増加しています。企業は主に、プロモーションやブランディング、リクルート、市場調査などの目的でこの予算を活用しています。
まちづくり活動自体が広告メディアとなり得ます。従来の協賛方法とは異なり、まちづくり活動を媒体化して企業の広告価値を創出することで、企業は広告費という認識で協賛金を継続的に支払うことが可能になります。これは団体と企業の双方にメリットがあります。
まちづくり活動を広告化するには
まちづくり活動を広告化するには、チラシやポスターの配布、SNSやWEBサイトでの発信、メディア取材、イベント開催、交流会など、多くの機会を広告化(広告価値創出)することがポイントです。 例えばイベント開催時には、ブランディングやプロモーション、直接的な訴求機会を企業に提供することができます。
さらに、地域貢献という意義ある活動を支援することで企業のブランド価値も向上します。
実際、まちづくり活動による広告効果はうまく活かす事が出来れば、通常の広告媒体より数倍高くなります。自治体のインフラやメディアを活用した高い発信力、新規顧客獲得、地域貢献によるブランド価値の向上など、多くの強みがあります。
弊社の事例
弊社の事例では、企画の収益化に以下のスキームを適用しています。
⑴ その他収入(出店料、委託金、入場料・参加費、補助金など)
⑵ 1社限定特別広告協賛(20万円〜150万円程度 最大540万円)
⑶ 数社限定広告協賛(3万円〜20万円程度)
多くの団体は⑴の収入のみを頼りにしますが、弊社では⑵や⑶の広告協賛を得ることで高い収益化を実現しています。
例えば、10名しか参加しない企画でも毎回25万円の特別広告協賛 を得ております。 なぜそれだけ得られるのか? それは広告という概念の為、当日の参加者数ではなく、その企画を通して得られる企業のプロモーション数と得られるブランディング効果を構築し広告商品として販売しているからです。
伴走支援においても、弊社のノウハウを活用し、80%以上の確率で収益化に成功しています。伴走支援終了後も安定的に収益を確保できるケースが多く、現在では講座や伴走支援に加え、ChatGPTを活用した仕組み化にも取り組み、収益化支援を強化しています。
まちづくり活動の広告化を活用すれば、間違いなく収益化は可能です。補助金に依存した事業の多くは継続性に乏しいですが、広告協賛を得られれば、補助金は本来の投資目的に回帰できます。
この記事はノウハウの一部を簡潔に紹介しております。
手法・事例の詳細は文字では全て書ききれない為、省かせて頂いております。
伴走支援では、プレイヤーの事業を通してノウハウを活用し支援・育成を行っております。